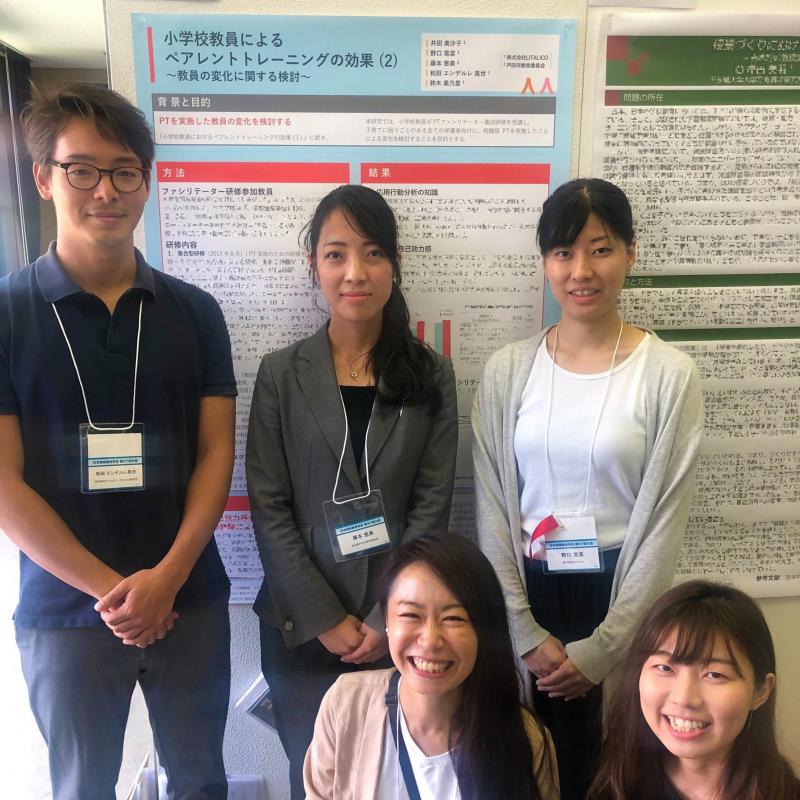「一緒にいれば分かりあえる」は幻想だ・・・小山田氏「障がい者イジメ」発言で注目、知られざる「ダンピング」の実情
2021.10.07【文春オンライン】
『ロッキング・オン・ジャパン』等、複数の雑誌で小山田圭吾氏が過去の障害者いじめを語り、東京五輪開会式の演出チームを辞任した問題は広く報道された。その際に、彼個人よりも、背景にある障害児教育の問題に目を向けていたのが野口晃菜博士だ。
インクルーシブ教育の専門家として各種委員を務めるほか、学校・自治体・民間企業などと連携して共同研究、仕組み作り、助言等を行っている野口氏は「ダンピング(投げ捨て)」という問題が障害児へのいじめの背景にある可能性を指摘する。重度脳性麻痺と発達障害を持つライターのダブル手帳(@double_techou)が野口氏に「ダンピング」について伺った。
「ただ一緒にいるだけでわかりあえる」は幻想だ
▼ダンピングとは何ですか。
野口晃菜博士(以下、野口▽)ダンピングを説明するために、まず「インクルーシブ教育」の説明をしますね。
これは日本だと単に「障害のある子とない子が同じ場で学ぶ」という意味で使われがちです。しかし本来は「ただ一緒にいる」のみならず、「合理的配慮」の実施も含意する言葉で、それが為されて初めてインクルーシブ教育といえます。
多数派の人のみを中心とした教育でなく、「障害」を含む多様な子どもの存在を前提とした教育をつくっていくことがポイントです。
たとえば読み書きの困難や色々な障害など、学び辛さを抱える子がいたとしましょう。既存の方式を彼らに強いると学ぶ機会を奪ってしまう。眼鏡の子に裸眼で黒板を読めと言うのと同じです。
そこで一人一人に合わせ、音読の代わりに読み上げツールを使う、黒板を書き写す代わりに写真を撮る、タブレットで入力する等々、本人と相談しつつ他の子と同様に学びにアクセスするための工夫をすることが「合理的配慮」です。
そうした工夫もなくただ一緒にいるだけ、障害のある子どもを通常の学級に放り込んでいる状態がダンピングです。
▼このダンピングは、いつ頃から問題になっているのですか。
野口▽米国や英国では70年代以降、障害のある子も同じ場で学ぶことが重視され、その機会が増えていった。その中で「何の工夫もなくただ一緒にいるだけでは逆に学びからの排除が起こってしまう」という指摘が出始めたという経緯です。
日本の場合、障害のあるなしにかかわらず、積極的に一緒に学ばせようという地域と、障害のある子どもは基本的に特別支援学級に通わせる地域があるなどかなり差があって、「ダンピング」以前に、子どもたちが一緒に学ぶ環境が、全国的に実現できていません。
▼小山田圭吾氏が通っていた小中高一貫校は、障害を持つ生徒を積極的に受け入れ、一緒に学ばせていたといいます。「子どもは一緒にいれば何もせずとも自然と分かり合える」と言う人もいますが……。
野口▽幻想だと思います。社会には「障害」という言葉があり、偏見も蔓延していて、幼い子もその中で生きてますから。
子どもは大人の言動や態度を実によく見ています。私が気になるのは、学校でも、家庭でも、メディアでもはびこる能力主義です。その下で学級経営をしたら、障害のある子はどうしてもできないことが目立ってしまい、「なんでこんなこともできないんだ」という感情を他の子から向けられたり、本人の自己効力感もどんどん下がっていったりしかねない。
だから、「できる」「できない」が最重要のものさしにならないように学級経営する必要がある。特別な工夫もなくただ一緒にいれば分かり合える訳ではないと思います。
▼現実にはそうした配慮を受けられてない障害児も多くいるでしょう。ただそれを是とする意見もあります。曰く、障害児にとっても、虐められたり、皆できることが自分だけできなかったり、といった惨めな経験こそ、社会の何たるかを体感するまたとない授業になる、と。割と上の年代だとこうした教育観の人は珍しくないと感じます。どう思われますか?
野口▽あり得ないと思います。私は成人した障害のある人と接する機会もありますが、その中には学校で一生分の傷を負った方もいます。そんな形じゃない学び方で教えるのが学校でしょう。
▼暴力を使わず学ばせる。
野口▽そここそ教育の役割なのに、それを放棄して、いじめや排除を正当化するのは虐待です。
得意不得意や「どんな時助けてほしいか」を口に出す
▼国が出している「合理的配慮」の事例集(※1)を読んだら「児童間でのコミュニケーションを増やす」「トラブルを未然に防止する」などと書いてあったのですが、学校側からの働きかけでこうしたことを実現するのは実際に可能なのでしょうか。
野口▽私が学校に勧めるのは、自分の得意不得意や「どんな時助けてほしいか」「こう接してほしい」等を考える授業を全員に行うことです。その中に障害のある子どももいたりするでしょう。でも自分の特徴を周囲に喋る力は、障害の有無にかかわらず皆に必要です。
人との距離が近すぎる子もいれば、一方的に自分のことを喋る子もいますよね。互いの特徴や適した意思疎通の仕方を知ればトラブルの未然防止にもなる。障害のある子どもだけ助けが必要なのではなく「得手不得手は皆ある」前提での学級経営が重要です。
▼小山田氏の炎上の際に複数の障害者団体が声明を出す中で強調されていたのが、いじめの懸念を理由に「障害のある子と無い子とを分けて教育しよう」という流れに傾くことへの危惧です。「ダンピングが悪いから分離教育が良い」とはならないわけですよね。
野口▽はい。ただ「いじめを受けるリスクがあるのなら別の場に」と思わざるを得ない状況も理解できますし、そう考える保護者も多いでしょう。
▼分離教育について考えさせられたのが、東京都教委が企業就労率100%を目標に特別支援学校への導入を進める特別なカリキュラ厶が人気との記事です(※2)。企業が障害者枠で雇用する人のために切り出す仕事は事務や清掃などの間接業務が多いため、就労対策もそうした業務中心の訓練とのことでした。
野口▽大学に進む障害のある人も今後増えるでしょうが、高卒ですぐ働く方がまだ圧倒的に多いです。だから特別支援学校の高等部では「18歳で自立しなきゃ」という理由で作業学習ばかり詰め込まれている印象です。その中で「うちに来れば就労できる」と謳う学校も出てくる。
それが高校の果たすべき役割かは疑問です。そのぶん部活や他の高校生が青春時代を満喫している活動に割ける時間は短くなってしまっています。
※1……独立行政法人国立特別支援教育総合研究所インクルーシブ教育システム構築「合理的配慮」実践事例データベース
※2……障害児向け「エリート校」が生まれる根本理由(東洋経済、2018年6月13日)
▼大学も就職予備校と揶揄されますが18歳と22歳の差は大きいですね。社会的に不利な障害者の方が実質的に4年早く人生設計を迫られる。考えれば不思議です。
野口▽本来逆ですよね。米国で私が見た学校では、障害のある人は22歳まで公教育において就労移行支援、地域移行支援を無償で受けられるんですよ。
▼大学に行かずとも4年の猶予がある。米国の教育から学べる点は多そうです。
野口▽もちろん米国にも課題は多いですが、私自身、米国イリノイ州で教育を受けたことが今の活動の原点でもあります。
小6の時に米国に引っ越したのですが、同じクラスに様々な障害のある子がいたんです。脳性麻痺で車いすに乗っていて首を少し動かすことしか難しい同級生もいました。
それまでそういう人に会ったことがなかったので衝撃を受けたし、日本ではどこにいるんだろうと思いました。その子はセンサー式のボタンで意思疎通していて「こういう技術を使えばコミュニケーションができるんだ」と興味を持ちました。
▼その子達の周囲との関係はどうでしたか?
野口▽皆「ハーイ」みたいな感じでいつもカジュアルでした。コミュニケーションを積極的に取っている人が多かったです。
あと私が米国にいた90年代~2000年にかけてはADHDと診断される人が増えていた時期でした。あくまで私が通った学校の話ですが、クラスにもかなりそういう子がいて、彼らが実に抵抗なくそれを話すんです。
「俺、ADHDだからちょっと保健室行って薬飲んでくるわ」みたいな。私にはすごく新鮮でした。でも他の子も「へえ」みたいな反応なので、私も「へえ」みたいな感じで。
多動で机に座って勉強できないんだけど、バスケが得意でドリブルしながら本読んでる友達もいました。そのほうが覚えられるらしくて。
「タブレットを持っていくと『ズルい』と言われる」
▼懐の深い教室ですね。逆の意味で印象深かったのが、野口先生が以前あるシンポジウムで発言されていた日本の話です。タブレットを使えば学習できて、他の子どもたちと一緒に授業を受けられる子でも「これを通常学級に持っていくと皆に『ずるい』って言われるから」と嫌がるケースが多いと仰っていますね。
野口▽学級経営の方法を工夫せず急に「あなただけタブレットで勉強しよう」と言えば本人も嫌がって当然なんです。今の教育現場には皆と同じペースで同じことをするのが正しいという価値観があり、生徒自身もそれを内面化していますから。
まずは、学級に「学び方は一人一人違っていい」と浸透させることや、本人が自分に合った学び方を知ることが必要です。
▼理解を醸成して初めてタブレットが活きると。
野口▽ええ。テクノロジーをただ導入するだけでは解決しません。
▼関係者が一致して地道な努力を続けられるかが鍵になりそうです。
野口▽ただ、「通常学級を選んだら何の支援も受けないよう覚悟しなさい」などと言って自己責任にする人も未だにいるのが現状です。
▼何か改善を要望しても「好き好んで普通学級に来たんだろ」とダンピングの正当化に使われる?
野口▽はい。これは先生個人よりも構造に問題があると思います。そもそも障害を理由に普通学級と特別支援学級の選択を迫られること自体、酷でおかしいんです。障害のない子どもはそうした選択をしなくてもいいわけですから。
当然に地域の学校に通い適切な支援を受けられるのが前提であるべきです。その仕組みを国として整備していかねばなりません。
「特別扱いはしない」が正しいわけではない
▼インクルーシブ教育を語る上でリソースの話は避けて通れません。
野口▽ええ。時に異なる障害種同士によるパイの奪い合いになることがあります。しかしその根本にはそもそもの教育予算全体が少な過ぎるという問題がある。従って、一致団結して全体のパイを増やしていくのが大事だと思います。
▼実際の教育現場に着目するといかがですか。
野口▽個々の合理的配慮を具現化するにあたっては、本人も含めた関係者間で「今あるリソースの中でどれだけできるか」の合意形成を図らねばなりません。
しかし障害を持つ子どもやその保護者と学校・教育委員会とが対立するケースもあります。
▼普通学級への就学を断られたり?
野口▽それもあるし、普通学級へ就学した上で、プリントを他の子よりも拡大してルビをつけてほしい、別室で試験を受けたい、タブレットを持ち込みたい等様々です。こうしたことに学校側が初めから「無理です」と対応したことが引き金になったりするんです。
合理的配慮の紛争を調停する独立した公的第三者機関を設け、そこが間に入り一緒に解決していく仕組みだと相当違うでしょう。本人が最大限自分らしく学び過ごすために何ができるか、各々が知恵を出し合えばやれることは沢山あります。
▼「皆に合わせろ、特別扱いはしない」と言われて育ったので、教育と合意形成は対極にあると思っていました。
野口▽確かに教師という人がいて皆を指導する側面や、皆が同じ時に同じ事をせざるを得ない場面もあるでしょう。
しかし国の方針も教育現場も、主体性を育む方向に進みつつあるのもまた確かです。例えば、先生だけが勝手にルールを決めるのではなく、生徒達自らが話し合って校則を見直す動きも現れています。
▼ルールは皆で作ってもいいし、その過程も学びである、と。
野口▽ええ。だから合理的配慮にしても「ずるい」みたいなことがあれば皆で考えたらいいんですよ。むしろそれは子どもに人権や障害を教えるチャンスです。先生が全て正解を持ってて渡すのではなく、子どもとともに考える。
「そうか、なんでずるいと思うんだろうね」とか「じゃあなんで合理的配慮ってあるんだろうね」とか。子どもたちが主体的に学び先生が一緒に考えながら支える。そんな教育観を大切にしたいです。
◆ ◆ ◆
なぜインクルーシブ教育が必要なのか
野口氏はダンピングを入り口にインクルーシブ教育の何たるかを語った。つまり障害児と健常児のお互いにとって、同じ教室で机を並べることが幸せな体験になるようにする知恵だ。
ただそもそも何故両者が同じ教室で一緒に学ぶべきなのか。これは健常者の中にはピンとこない方もいるかもしれない。
私が考える最大の理由は、子供の頃から両者の接触機会を多く確保しておかないと、障害者の存在が忘れられたまま回っていく今の社会が続いてしまうからだ。
今回の問題にせよ、小山田氏の報道は過熱する一方、虐められる側の障害者の存在は置き去りにされた。
彼が自身のサイトで公式の謝罪文を掲載した数日前、私はヤフーニュースで彼のインタビュー記事を見つけ、コメント数の膨大さに圧倒された。それはさわりだけの無料記事で話の中身は殆ど不明にも関わらず、想像を絶するほどバズっていたのだ。
しかしメディアが彼への取材を熱心に試みたのとは対照的に、障害者の側の話はこの間ほとんど聞かれなかった。仮に当時の直接の関係者に当たれずとも、現在や過去に虐められた経験がある障害者、保護者、障害者団体、障害児教育に携わる教師など、この問題を語れる人は多い。彼らに発言の機会を与える努力がもっとあって良かった。
こうした報道姿勢と障害者への関心の低さは強力なサイクルを形成しており、メディアはあまねくこの構造に囚われている。大切なことでありつつもメディアを介して伝えるのはとてつもなく難しいメッセージは多い。それは私自身も、何かを発信する側に回った時に思い知らされることだ。ここでは特にそのうちの三つを挙げたい。
第一に、報道に登場していなくとも私達障害者は絶えずどこかに存在し続けていること。悲惨な事件や旬の話題が起きた時だけ瞬間的に現れて消える陽炎ではない。
第二に、私達は露悪的なキャラを作るためのアクセサリーではないし、人を社会的に抹殺するための武器でもない。つまり何かの目的のために作られた道具ではないということ。
第三に、私達は何らかの行為の対象や目的語になるだけでなく、行為の主体、動詞の主語にもなれるということ。
私達も人間である以上はどれも当然だ。しかし常に肌感覚として持てる人がどれだけいるか。そう簡単なことではないし、まして報道を介してやり取りできるたぐいの感覚ではない。
それを培うには同じ空間で一緒に長い時間を過ごす経験が必要であり、インクルーシブ教育への期待は大きい。幼少期の経験から私達を頭の片隅にでも置いてくれる人が増えていけば、報道が変わり、制度が変わり、社会が変わる時が来るだろう。
----------------------------
※野口 晃菜
株式会社LITALICO執行役員 LITALICO研究所所長
1985年生まれ。小学校6年生の時にアメリカへ渡り、障害児教育に関心を持つ。高校卒業時に日本へ帰国、筑波大学にて多様な子どもが共に学ぶインクルーシブ教育について研究。その後小学校講師を経て、現在障害のある方の教育と就労支援に取り組む株式会社LITALICOの執行役員・LITALICO研究所所長として、障害のある子ども8,000名への一人ひとりに合わせた教育の実現のための仕組みづくり、公教育や児童養護施設との共同研究などに取り組む。共著に「インクルーシブ教育ってどんな教育?」や「地域共生社会の実現とインクルーシブ教育システムの構築―これからの特別支援教育の役割」などがある。博士(障害科学)。
----------------------------
長い記事を引用したのは、記者のスタンスよりもインタビューに答える野口さんの明快さに惹かれたからです。彼女の話は5年程前にLITARICOの長谷川社長の話の前座?で聞きました。とにかく長谷川社長も野口さんと同年齢で、会社全体が若武者集団と言う感じでした。創業が2005年から就労移行支援事業を皮切りに、全国展開の障害者福祉の会社に急成長して、2000名を超える従業員を擁しているのがLITALICOです。日本の障害者福祉に新しい時代が来たなのと感じさせてくれました。
もっと、驚いたのが、こうした福祉や教育ベースの研究は大学研究者や政府関係の研究所所属の研究者が行うものという常識を覆し、会社の中にシンクタンクをもって自分たちの理念を企業ベースで進めようとしている事でした。もちろん、現在の福祉や教育関係の民間事業所でかつて研究者だった人が経営している法人はいくつかありますが、シンクタンクが持てるほどの資本力があるところはここだけです。
LITALICOの経営が全て上手くいっているわけではないし、マニュアル対応に傾きすぎてサービスに合わない利用者が離れていく傾向も耳にしますが、サービスコンセプトがはっきりしているので全体の療育や就労支援の方針がぶれる事はないと思います。野口さんが米国やイリノイ州の教育を正確に紹介してくれているので、インクルーシブを目指す我々には貴重な示唆を与えてくれています。若いと言うのはまっすぐで良いなと思います。
LITALICO研究所 facebook.comより