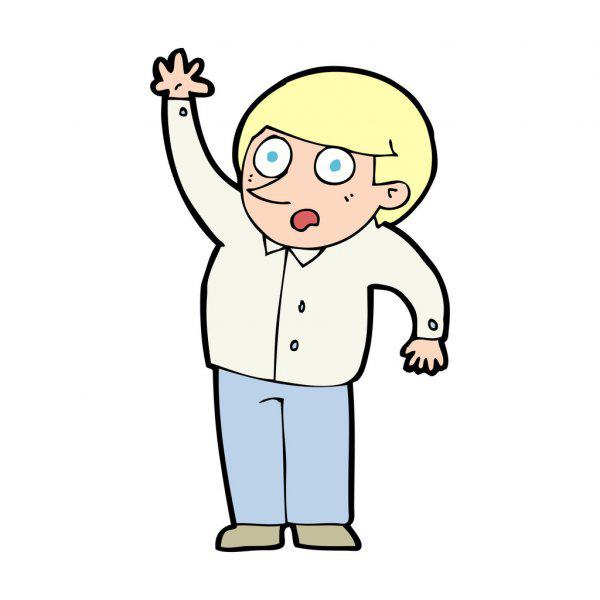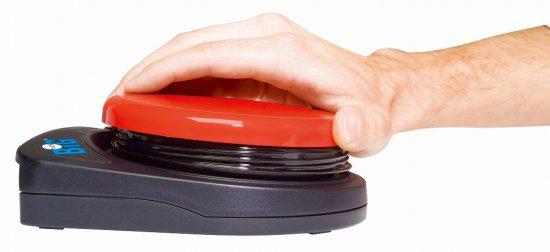今日の活動
昨日はすみませんでした
P君をいつも通り学校に迎えに行くと、「昨日はすみませんでした」と突然頭を下げて謝るのです。「いえいえ別に何とも思ってないよ」と言って恐縮しましたとスタッフがいいます。スタッフが子どもから自発的に次の日に改めて謝罪されることが、これまで一度もなかったので驚いたという話です。
P君は前日、公園に水筒を忘れたのです。「水筒忘れてきたから、取ってきてほしい」とスタッフに言いました。「え?君の水筒を探すなら、『すみません。水筒を公園に忘れてきたみたいなんで、一緒に探しに行ってほしいです』と言ってください」とスタッフに窘められます。「取ってきてくれてもええやん!けち!」とP君は逆切れしました。
結局、二人で探しに行ったのですが、スタッフは「車の中で待っているから、まずは自分で探しておいで」と促すと自分で探せたそうです。話はここまでなのですが、支援を受けている子に依存的な言動が多いのが気になるという話をそのあとスタッフ間で話していたのです。忘れ物も多い、落とし物も多い、不器用で物を壊しやすいなどがあって、ついつい大人が手伝ってしまう事が多いことが原因かもしれません。大人は手伝っているつもりが、当の本人は自分の事でも大人がするものという誤解をしているのかもしれません。
でも、P君は「自分のものは自分で探せ」と大人に言われたのが初めてだったのかもしれません。自分で探したことも初めてだったのでしょう。そして、自分で見つけた時に嬉しかったのかもしれません。きっと一晩中そのことを考えていたのでしょう。「先生ごめんね」をどう伝えていいか考えていたのだと思います。それが、いきなり「昨日はすいませんでした」だったのです。迎えに行ったスタッフはとても嬉しかったそうです。
滑り台
Oちゃんが初めて滑り台に上がって足から滑り降りました。スタッフみんなで大喜びです。滑り台は発達的に考えると2歳を超えると滑れるようになります。1歳なりたて児の滑り台の滑り方で一番よくあるのが、スロープをよじ登って力尽きて腹ばいに落ちてくる子です。次は階段を上がって踊り場でそのまま頭から滑る危ない子です。つまり、姿勢の転換ができないのです。
滑り台は1歳半の節目を試す遊具でもあります。登ったら姿勢を変えて足から滑ります。つまり、遊具に合わせて体を調整しているのです。ここから、場面に沿う、指示に沿う力が芽生えてくるのです。それまではお母さんの真似がしたくて、櫛を反対向けていたのが毛の方に向けたり、スプーンで茶碗をたたいていたのが落とさないで抄うことに気が付いたりと、意味を操作で理解していきます。なので、Oちやんの滑り台の踊り場での姿勢転換(座ったままの足の入れ替えでしたが)はすごいことなのです。
スノードーム
透明な容器のなかに雪景色を再現するインテリア、スノードーム。好きなオブジェを用意して、雪に見立てたキラキラ素材と一緒に、水で薄めた液体のりを入れるだけで完成です。ジャムの空きびんや 100円ショップのふたつきびんのほか身近にある素材を使って、クリスマスにぴったりなスノードームが簡単に作れます。
今回は、スヌーズレン用(ビーズがゆっくり舞うのを楽しむため)のスノードームを作りました。ラメ用にホログラム折り紙とマルチカラーの極小ビーズがびんの中でふわふわと舞う、ロマンティックなスノードームです。言葉のない障害の重い人でも楽しめる、ふわふわキラキラワールドが簡単に小さなびんの中に完成。
N君が「サンタは置かないの?」と聞いてきましたが、今回はスヌーズレン用に作ったので小物を用意していませんでした。空きびんのふたを下にして、雪だるまやモミの木を接着剤で貼り付けて置くともっと素敵になるので次回はこれに取り組みます。
相貌失認
今日はお天気がとてもいいので西山歩きにいってきました。L君は久々の運動が西山歩きだったので帰ってくるころにはスタミナ切れで、青息吐息でぐったりしていました。そのL君にM君が矢継ぎ早に漫画の話題を話しています。M君は一つ年上のL君がとても気に入っていて、L君が来るととても嬉しいのです。それがわかるL君はぐったりしながらも「うんうん」とM君の話に頷いています。L君の優しさには頭が下がりますが、M君はそんなL君のしんどそうな表情がまるで認識できないようなのです。
相貌失認(そうぼうしつにん、Prosopagnosia)とは、脳障害による失認の一種で、特に「顔を見てもその表情の識別が出来ず、誰の顔か解らず、もって個人の識別が出来なくなる症状」を指すそうです。これは頭の怪我などからわかってきた障害ですが生まれつきの人もいます。ブラッド・ビットが2013年に相貌失認かもしれないと告白しましたが、ASDの人たちの中にも程度の差は人によってそれぞれですが少なくないようです。
M君は3年ここに通所してますが、いまだに「あの人」と名前が覚えられない子どもやスタッフがいます。人に興味がないというより、顔が覚えられないのかもしれません。そして、大好きな人の表情も読みにくいので、しんどそうに頷いているL君に自分のお気に入りを話し続けているのです。こんな時、どんな支援がいいのか考え込んでしまいます。表情が見えないのに見ろというわけにもいかないからです。
この場合は、まず自分が他者の顔や表情が読みにくいことを知り、そこから起こりうるリスクとそのリスク回避の方法(謝り方等)を学んでもらう事と、極身近な人たちにはカミングアウトして援助を求めていくのが良いかなと考えています。筆者も相貌失認の傾向があり、スーパーなどで買い物をしていて親しげに声をかけられても誰か思い出せず「急いでいるので」と買うものも買わずにその場を逃げ出すことがたまにあります。研究によると人口の2%にこの傾向が確認されるそうです。
アセスメント
支援で最初に重要なものはアセスメントです。医療でも診断がまず大事です。どこが痛いのかまず調べます。頭が痛い人に消化薬を処方したり、腹痛の人に頭痛薬を出さないのは当たり前です。ところが、教育や福祉の現場ではそれがちょくちょくあって、悪意はないがいつまでも頭痛の人に消化薬を出し続けていることがあります。この間違いの多くの原因は教条主義とアセスメントを動的に捉えられないPDCAサイクルの欠如です。
K君は表出のコミュニケーションが弱いと言われてきました。ASDの人ならある程度言語がわかるのに不適切な行動をしている場合は、まず表出のコミュニケーションの弱さを疑います。それで大体の子どもはアセスメントOKですが、うまくいかない場合があります。表出を支援している場所なのに不適切行動が減らない時や、他の生活場面では不適切行動がないとするなら、表出以外に何かあるなと考えてこれまでのアセスメントを疑ってみます。
課題が難しい、生活がつまらない、褒められることが少ない等が考えられます。しかし、どんな子でもそんなに自分のことは分かってはいません。ですから、「自分はOK」と思える生活かどうか、「好きなことがある」のかどうか、「君なかなかやるね」と褒められる人がいるかどうか等をトータルに見直す必要があります。また、弱いところだけに着目した療育は必ず失敗します。必ず強みや得意なこと楽しいことと組み合わせて実施できているかも重要です。K君の生活を見渡せるほどの放デイの利用回数がないので分析は難しいのですが、定点観察をしながらアセスメントをすすめたいと思います。
カタトニア
J君に、大好物のおせんべいをメニューに示しているのに「おやついりません」といいます。どうも調子が悪いようです。顔色もよくありません。他の様子を観察すると、自立的なスケージュール行動はできていたはずなのに、その日はスタッフが誘導しないとなかなか動けませんでした。
J君にはカタトニアが時々出ます。カタトニアが出ているなと判断した際は、J君のタイミングで行動が切り替えられるように、いつもより本人と距離を取って待つようにしています。ただ、どれくらい待てばいいか、状況を見ていつ声掛けをするかは、本人の状態もあるしスタッフによって差があるもの事実です。
ASDにカタトニアの症状が出るのは、10代中盤の中学生ぐらいから20代前半ごろと言われ、期間も数ヶ月程度のものから数年間にわたる物まで幅広いです。カタトニアと思われる症状には、動作の停止、動作の遅れ、行動のやり直しなどが有ります。
飲食時の動作では、飲食の際に自分から動き出せずに止まってしまったり、摂取する動作が非常に遅く定められた時間内に食べられない事があります。本人のお腹の調子が悪かったり食べたくないのかと思い片付けると、「食べる」と訴え最後まで食べることもあります。場合によっては自分ではお皿から口まで食べ物を運べなくなってしまい、周りの大人が介助をして食べさせることもあります。飲食の遅れがあると時間内に食べ切れず、体重が減ってしまう事もあり注意が必要です。
室内の移動や屋外への移動、車に乗り込む際などに動けなくなったり、移動がとても遅くなる事があります。動けなくなってしまったときにカウントダウンや様々な声かけで促したりしても動くのが難しく、移動するのにとても時間がかかる事があります。自宅でも外出時には1時間ぐらい前から移動を促したりしても、学校のスクールバスなどに間に合わない事もあります。また、移動の際に部屋の敷居や段差などがあると、そこをまたごうとする行為で止まったり、何度もまたぐ動作をやり直したりする行動が見られる事もあります。
トイレで排尿の際に便器まで行きズボンとパンツを下ろしますが、そこで止まってしまい排尿をする事もパンツやズボンをあげる事もできなくなることもあります。また、本人は既に何度も行って理解している作業や動作にもかかわらず途中で止まってしまい、周りからの指示や促し、場合によっては体を押して前に進ませたりさせないと次の動作が行えなくなってしまう事もあります。
カタトニアは、指示をしても抵抗して嫌がる場合もある(周囲には嫌がっていることも伝わらない時がある)ので穏やかにかかわる必要があります。治療方法には薬(向精神薬等)による治療方法があります。カタトニアの原因や症状により治療方法や服薬する薬が変わってくるため、専門の医療機関での診断が必要です。
ホームページのお休み
毎度ご愛読いただきありがとうございます。
ホームページ等のメンテナンスのため12/16水曜まで掲載をお休みします。しばらくお待ちください。
しんどいです!
前回お話していたW君の交渉は進行中なのですが、先日W君は自分で契約した回数ができないと訴えてきたのです。10本を二回やると契約したのですが、2回目の時に「しんどいです。やりたくないです」と訴えてきたのです。スタッフの偉いところは「たかが缶潰し10本じゃないの」とはいわずに、「そうですか。では今日はやめましょう」と受け止めたことです。
W君のしんどい中身は良くわかりませんが、作業中にこんなことを言ったのは初めてなのです。たいがいは、始まるまでに「いやです」「しません」か少量付き合い程度に作業するかだったので、今回のような中断の要求は出しようがなかったとも言えます。でも作業中に彼としては思うところがあったのでしょう。その契約の内容がまずかったのか、本当に途中でやるせなくなったのかはW君にしかわからないことですが、彼の発言は尊重したいし、契約の仕方にもう少し工夫ができないかどうか次に生かそうと話し合いました。
熱い心と、冷たい頭
子どもの検査所見にはいろいろあります。観察は素晴らしいのに、で、どうするの?と具体的な支援が見えない場合があります。『何を指示しても嫌だ嫌だと拒否するI君(4歳児)の相談があったので、検査を行いました。検査者と関係が持ててきたので、模写課題をやってみようとしました。I君検査者が持っている模写カードを盗み見していて「簡単なのは嫌やで」というので難しいかなと思ったのですが正方形模写(3:6)に挑戦してもらいました。
「見んといてや」と隠すように正方形模写に一生懸命取り組みました。できた模写を見てみてみると、四角の頂点がどうしてもうまく描けず、何度も修正してモデルの絵に近づけようとした軌跡が描かれています。なりたい自分への葛藤というI君の願いがそこには表れていました。嫌だと言うI君を頑張れと追い込むのではなく、I君が自分の力で取組もうとしたり修正してくるタイミングを大事にしてあげたいものです』
I君への思いが美しい表現で綴られています。でも、これでは「ちゃんとしなさいと追い詰めないで待つように。そのうち自分で取組むと思うよ」としか読めません。嫌の原因はできないかもしれないという不安が高まるからだというのは良くわかりますが、大人の側が追い込んでいるからというだけが理由だろうかと、応用行動分析では考えます。「課題の与え方がボトムアップでゴールに届きそうにないから嫌なのかもしれない。トップダウンで見通しのある届きそうなところから取り組ませれば自信になりはしないか」と環境側にその原因を求めます。
子どもの内面の物語(スジ書き)を作ってしまうと、環境側や大人側の課題が見えなくなる可能性があると思うのです。子どもの内面だけでなく、子どもの外側に問題がないかどうか考えてみること、できるために何が足りないのか考えてみること、それが子どもをリスペクトする専門家の仕事だと考えています。学生の頃、お花畑のようなことを言って、先生から「情緒的な言葉は時として私たちから真実を遠ざけることもあります。熱い心と冷たい頭を持ちなさい」と言われたものです。
『熱い心と、冷たい頭をもて』アルフレッド・マーシャル (イギリスの経済学者)
祝500万ビュー!
祝500万ビュー!
本日でこのブログは500万ビューを達成しました!昨年4月から1年で100万ビュー、この4月から8か月で400万ビュー増加なので指数関数的に増加していると言えます。先日も見学の保護者の方から、利用しているサービスからスケジュールへのトランジションについて見直しをしているという話を聞きました。
え?それどこかで聞いたような。あ!それ私です。ブログに書いた覚えあります。見学者の方が教えてくださったサービスは我々のブログのフォロワーさんのようでした。こんなふうに身近でも読まれているのかと知ると、嬉しいような怖いような不思議な気持ちです。毎日1万回以上読まれるのは、何か共感してもらえるものがあるだろうと思います。
ということで、この500万ビューを次の1000万ビューの跳躍台にして、皆様のご期待に添えますよう職員一同精進して参りますので、どうぞよろしくお願いします。この調子で行くと来年度には1000万ビューに届きそうです。敢えてコメント欄は設けていないのですが、ご意見やアドバイスがございましたらオフィシャルアドレスまでメッセージをお願いします。
やればできる人
G君は高等部生ですがシャイな人なのでスタッフに声をかけられないとなかなか自分から進んで事が起こせません。トイレですら「大丈夫ですか?」と聞かない限り自分では行かないで我慢しています。
そのG君が、近ごろ新入りのH君と仲が良くなり二人だとちょっと元気になって、H君がいれば様々な新しい課題でもトライするようになってきました。かなり自信ついてきたねとスタッフも評価していました。友達の力は本当に偉大です。
そんなある日、別の学校の中学部生が事業所に見学に来ました。G君はチラチラと新参者を見て気にしているようです。すると、何と言うことでしょう!ストラックアウト・ゲームはいつもヘロヘロ球だったのに今日はバシッと速球で決めてきます。声もでかくなって、「俺はやるよー」と豪語しています。そして、なんとスタッフに「トイレ行ってくるわー」と言うのです。「え?ついていかなくていいですか?」「イランイラン」と手を振ってトイレに一人で行きました。新参者の中学部生が見ているとはいえ、やればできる人だったのです。後輩の力も偉大です。
スケジュールとタイマー
F君が家からタイマーを持ってきているというので、どんな使い方をしているのか聞くと、机の横にセットもせずにおいているだけと言います。では休憩時間はどうやって終わるのか聞くと、そろそろ片づけてほしいタイミングでタイマーセットしてタイマーが鳴ったら声をかけて終わらせていると言います。この使い方では「終わりやで」と声をかけているのと変わらないです。でもこれは支援「現場あるある」事象です。なんのためにツールを使うか良くわからないまま支援の中にツールが入りこむ悪い例です。またF君自身も何のためにタイマーがあるかわからないけど、机の上にこれがないと不安なので家から持ってきているのだと思います。
タイマーは小学生から障害の重い高等部生までよくタイマーを使いますが、どんな目的で使っているのか聞くと、大人の都合で使っているだけだと言うことが少なくないです。タイマーを使うのは子どもが自発的に次の行動に移るために使うのですが、それを理解させるにはスケジュール操作を丁寧に教える必要があります。
タイマーは休憩時間や遊び時間に使うことが多いですが、これをタイマー理解の導入に使うのは間違いです。楽しいことが終わる行動が強化されるはずがないからです。重度の人には楽しいことが来る時間にタイマーを設定します。小学生には、自立的にタイマーで行動ができたらポイントをあげるという形でタイマーを教えます。
こういうことが定着したうえで、休憩時間にタイマーを使ったり、作業を途中でやめるためにタイマーを使い、自立的にスケジュールを操作できるように支援すればうまくいくはずです。
いいえ・違います
E君が遊びたいかなと、「音のなる絵本」をスケジュールに入れておきました。E君がその絵カードを渡してきたので、いつもの音のなる絵本を渡すと、押し返して自分の頭をたたくのです。そうか、新しい音のなる絵本が欲しいのかぁと新しい本を渡すと遊びだしました。
E君は絵カードでかなり要求ができるようにはなっているのですが、カードの弁別が十分にできないのと「違う」が自分の頭をたたく行動になっていることです。確かに頭をたたけば「違う」ことは誰でもわかりますが、もっと穏やかな拒否の方法を探しています。
手で押しのけるのはいいのですが、拒否を強く伝えるために言葉のない人の中では自分の頭をたたく人は少なくありません。これを穏やかな身体サインに変えたいのです。ところが、「いいえ」「違います」のトレーニングは簡単そうで難しいのです。
PECSでは身体プロンプトで首を振らせて拒否のサインを教えるように提案していますが、背後から手を添えて首を左右に振らせるのは難しいのです。顔を触ることで、本人の「何すんねん!」の反応が出ることが多いからです。なので、両腕を出して「NO」の表現の方がいいかもしれません。要は頭をたたく行動から代替させやすい行動がいいのです。さてどんなサインがうまくいくでしょうか?
先輩はつらいよ
「外遊びの科学的根拠12/02」で掲載したように、B君C君は外遊びに行こうかと誘うと、「え~」となるのでビタミンDを強化子にして外遊びに誘い出しています。しかし、そんなことをしなくても「高学年のプライド」とという素晴らしい強化子を発見しました。
低学年のD君が「鬼ごっこがしたい」と言うと二人とも、「ええよー」と頷くので、「あんたら いつもとちゃうやん」とスタッフは思っていました。しっかり走り回って全員つかまって帰りましょうかという雰囲気の中、スタッフが言ってみました「もう一回しようか?」BC君そろって「却下!」と言います。「Dちゃんどうする?」と聞くと、「もう一回やりたい!」BC君揃って「しょうがないなー もう1回やろか」ということになりました。
延長戦も終了し、「さぁ 帰ろ帰ろ」と言うBC君の背中にD君が「もう一回したい」と声を掛けました。 さすがに「え~~もう帰ろうや~」と絶叫します。スタッフがD君に「D君どうする?」と聞くと「もう一回したい!」「このようにD君はリクエストしていますが…」とスタッフが言うと、「ほんな やろかぁ」と3回目も肩で息しながら付き合う高学年二人でした。先輩はつらいよ。
ボール投げ
Z君が公園でAさんとボール投げをしてにこにこしているという報告がありました。Z君はこれまで「前庭覚ニーズ」が高いと外出しては公園でブランコという日課が多く、小さい子が室内でうるさく叫ぶと他害もあり、他の子どもとはあまり交流せずにスタッフと過ごしてきた経過がありました。
しかし、他害の原因は他の子どもの大きな声が耐えがたく攻撃するというものですが、Aさんなど小さい子がうろうろするだけでイライラする様子もあったので、少し一緒に遊ぶなど交流させてはどうかという提案をしました。公園に行ってブランコをするだけではなく、Aさんとボール投げに取り組んでみました。スタッフと3人で取組んでAさんが受け損ねるとZ君が走って取りに行くなどの変化がみられています。
他害などがあると、なかなか他の子どもとの交流を避けがちですが、他害の関係を打ち消すほどのものかどうかは分からないけれど、一緒に楽しく活動する関係をどう作っていくのかも考えていく必要があると思います。
外遊びの科学的根拠
小学生高学年のY君らは「外で遊びたくない、面白くない」とよく言います。じゃぁ室内で何がしたいのと聞くとゲームかパソコンです。放デイ以外の日は外で遊んだことなどないというのです。友達もいないし、だいたい高学年は習い事で時間も合わないという悪循環で、友達と交流するのは学校か放デイだけだというのです。
外で遊ぶと、①太陽の光を浴びることで基礎代謝があがる②体を動かすことで心肺機能が高まる③空腹感を感じることで食欲がわく④睡眠の質があがる⑤生活のリズムが整う⑥運動することでストレス発散となりポジティブ思考につながる。ことを、丁寧に医学心理学的に説明しています。
丈夫な骨を作るためには、運動や日光を浴びてビタミンDを増やすことが重要で、夏は紫外線量が多く、ビタミンDを短時間で効率的に増やせるから夏に背が伸びやすく骨折もしにくいと説明します。背は高くなりたいと皆思うようでしぶしぶ外に出ています。あと、抜け毛は諸説あるので原因は一つではないけど、有酸素運動とストレス防止と抜け毛防止は関係があるという人もいるらしいというと、男の子は靴を履きだします。ただし頭皮に紫外線はほどほどにねと帽子を渡します。みんな、外で遊ぼう。
VOCAの意味
VOCAは、Voice Output Communication Aidsの略で音声出力会話道具が直訳になるでしょうか。大事なのはOutput(アウトプット)=出力というところです。言葉のない人の音声言語の代わりに使う道具という意味合いが重要です。人は、人から促されて喋ることはほとんどありません。自分が必要な時に自分で喋るのです。
XさんのVOCAの使い方は、先生が手にVOCAを持った時に「おかわり」と、Xさんがボタンを押しに行くという報告がありました。「え?それって『大人がおかわりと言いなさい』と言った時だけ喋れという指導と同じですよ」と他のスタッフが言いました。その通りです。自分から音声出力する=自発性言語を育てるはずのVOCAが受け身(応答性言語)の道具になっているのです。
肢体不自由の人は移動・食事・排泄など依存的になることが多いです。しかし、電子機器などを使えば、自分の意志を伝えることは可能なことからVOCAが生まれました。もちろん最初は身体プロンプト(後ろから手を添えて操作させる)をするなどしてVOCAの意味を教える必要があります。ただ、教え方は自発性を担保する教え方でないと、そばに人がいないと伝えられないとか、VOCAを人に持ってもらわないと使えないようになってしまいます。本人が操作しやすい位置にVOCA専用台を作る等いろいろ工夫して、自分だけの力で操作できる環境を整えようと話し合いました。
うるさい
すてっぷには、低学年から高等部生までの子どもが毎日10人前後出入りします。当然、はしゃぐ子もいたり、室内での声の大きさのルールがわからない人もいます。ところが、活動する部屋は一つですし、広さは40畳以上あるのですが、それでも大声は響きます。ASDの人の中には突然の大声がたまらなく嫌な人がいます。イライラしているとそれが他害につながったりするので、職員は部屋の使い方にはナーバスになります。
うるさくてイライラして壁を叩くなどの行動がある子どもには、「うるさい」「しんどい」をスタッフに伝えることで幾分楽になる人もいるので積極的に自分に気持ちを表出する練習をしています。しかし、それも度重なると我慢の限界を超えます。大声を出す子にはルールを教えます。声のレベルメーターでわかる子はいいのですが、それが理解できない子の対応はとても難しいです。うるさくしても注目しないようにはしますが、静かにすれば利得があるわけではないので教えるのが難しいです。何かいいアイデアはないか考え中です。
交渉
W君に作業の打ち合わせで10本の空き缶つぶしをお願いすると、W君は「8本」と交渉してきました。そこで、スタッフ側も「では5本で休憩入れて2回のインターバルでお願いします。」と再交渉すると「わかった」と契約成立しました。「おやつは何がいいですか」と聞くと「グミ8個!」とさっきの「8」を引きずっている様子なので、「グミ2個を2回でどうですか」と聞くと「わかった!」とこれも契約が成立しました。
わずか10本の空き缶つぶしですが、言われたからやるのではなく、報酬も要求しながら自発的に取り組んでほしいという願いが私たちにはあります。もちろん言い値で了解するのではなく、お互いに駆け引きしながら合意していくプロセスを大事にしたいのです。今は、作業の量ではなく取り組むときの質=受け身ではなく自発性が大事だと考えています。
正しいコミュニケーション学習
お話の出来ないU君は、何かをお願いするとき片手で頭を押さえてお辞儀をします。それがとてもかわいい仕草に見えるので、大人はついついリクエストしていました。新しく入ってきたスタッフがその様子を見て悪気はないにしてもリクエストしているのは疑問に思うと言ってくれました。
おそらくこの行動は、最初は大人が頭を下げるように手で押さえて教えていたのが、いつの間にか、自分の手で頭を押さえてお辞儀するようになったのかもしれません。
彼は今PECSのフェイズ3で要求物を選んでお願いができるようになっています。それでも、大人があの仕草を求めて自然に待ってしまうタイムラグがあるので、お辞儀も続けてするのです。それは良くないだろうというのがスタッフの意見です。確かに、可愛いからと言ってこちらの基準でお願いのオプションを求めるのはおかしな話です。今まで怒ることで要求が叶うと思っていたU君が自発要求していているのですから、そのことを第一に喜んであげて、早く要求のものを渡してあげてほしいのです。
同じように、VOCA(音声出力ボタン)の練習中の子に、大人は「ただいま」とか「ありがとう」などから教えたいと思うのが人情ですが、まずはボタンを押せば自分の要求が叶う事がVOCA練習の1丁目1番地です。つまり「おやつほしい」とか「喉乾いた」とか「おかわり」「もっとほしい」です。これが結び付けば、自分の意志で言葉(ボタン)を選ぶ方向に結びつきます。大人の求めていることと子どものコミュニケーション学習の順序は違うのです。